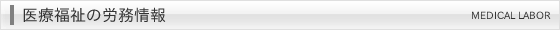今回は、無断欠勤により連絡が取れない職員の対応に関するご相談です。
先月採用した職員が、連休明けから突然無断欠勤となり、出勤しなくなりました。何度も電話をかけたり、メールを送ったりしていますが、まったく連絡が取れません。
このまま無断欠勤が続いた場合、退職扱いとしてよいのでしょうか? 今後どのように対応すればよいかを教えてください。
現段階では、職員本人の退職の意思が確認できないため、退職扱いとすることはできません。
引き続き電話やメールで連絡するほか、自宅を訪問したり、家族などへ連絡したりすることで所在と安否の確認に努める必要があります。個人的に連絡先を知っている他の職員から、連絡してもらうことも考えられます。
 無断欠勤となる状況には、本人の意思で出勤していないこともありますが、体調不良や事故に巻き込まれて出勤できないという可能性もあります。まずは、本人へ電話やメールで連絡することを継続し、また自宅を訪問するなどして所在と安否の確認に努めましょう。
無断欠勤となる状況には、本人の意思で出勤していないこともありますが、体調不良や事故に巻き込まれて出勤できないという可能性もあります。まずは、本人へ電話やメールで連絡することを継続し、また自宅を訪問するなどして所在と安否の確認に努めましょう。
それでも所在が分からず、安否の確認が取れない場合は、個人的に連絡先を知っている他の職員から連絡してもらったり、身元保証人や家族などから本人に連絡を取ってもらったりすることの検討も必要です。
本人と連絡が取れ、退職の意思確認ができた場合には、退職手続きを進めることができます。その際には、退職日、退職理由などを確認できるよう、退職届を提出してもらうことが望ましい対応となります。
さらに、本人と連絡を取った日時やその方法、対応者などの情報も含め、退職までの経緯を記録に残しておくとよいでしょう。
本人と連絡が取れない場合、本人の退職の意思が確認できないため、自己都合による退職として扱うことはできません。
医院が退職として扱うのであれば、解雇の手続きを進めることになりますが、解雇はその旨が本人に伝わらないと有効にはならないため、本人と連絡が取れない場合は、裁判所の掲示板などに解雇する旨を掲示する「公示送達」の手続きを行うことになります。公示送達では、2週間後に解雇の効力が発生しますが、手続きが煩雑であるため、行われることは稀です。
本人と連絡が取れない場合でも、就業規則に次のような規定がある場合には、自然退職として手続きを行うことができます。
- 例:職員が無断欠勤し〇日以上経過した場合には、経過した日の翌日をもって自然退職とする。
ただし、この規定があったとしても、本人に連絡を取り続ける等の対応は必要です。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 人事労務Q&A 〜半日単位の年次有給休暇を導入する際のポイント〜2025/12/31
- 人事労務Q&A 〜今後変わるパート職員の社会保険の加入要件〜2025/11/30
- 人事労務Q&A 〜体調不良で欠勤が続く職員に対する休職発令〜2025/10/31
- 人事労務Q&A 〜育児と仕事の両立のために柔軟な働き方を実現できるようにするための法改正〜2025/09/30
- 人事労務Q&A 〜育児休業給付金に上乗せで支給される出生後休業支援給付金〜2025/08/31
- 人事労務Q&A 〜育児短時間勤務をしたときに支給される育児時短就業給付金〜2025/07/31
- 人事労務Q&A 〜マイナンバーカードの健康保険証利用〜2025/06/30
- 人事労務Q&A 〜介護休業の対象となる家族と要介護状態の判断〜2025/05/31
- 人事労務Q&A 〜通勤手当を支給する際に考えておきたいルール〜2025/04/30
- 人事労務Q&A 〜就業規則変更手続きに必要な職員代表の適正な選出方法〜2025/03/31
- 人事労務Q&A 〜所定労働時間6時間以内のパート職員に対する休憩時間〜2025/02/28